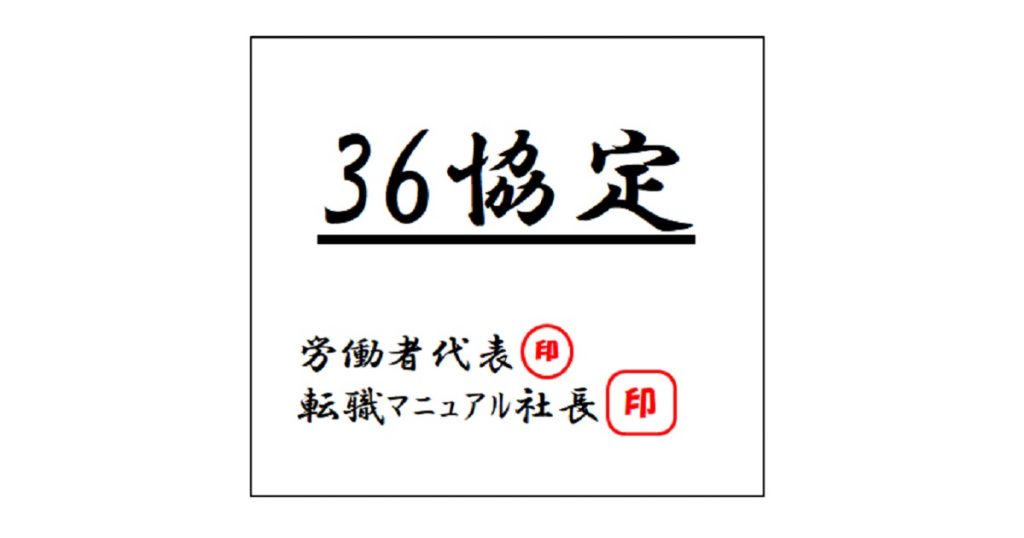(2020-7-11更新)
働き方改革の目玉政策である高度プロフェッショナル制度(高プロ)って、実際にどんな人たちが対象になるのかいまいち分かりにくいですね。
「年収1,075万円以上」
金額ばかり先行してしまっていますので、厚生労働省が発表した対象業務を確認してみたいと思います。
また、高プロ制度が実際にどのくらい活用されているか、実施状況を解説します。
高度プロフェッショナル制度とは

安倍総理の目玉政策である働き方改革のひとつで、労働者の合意を条件に、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とすることができる制度のことです。(2019年4月1日から実施)
ただし、高プロには次の条件を満たしている必要があります。
- 本人の同意を得る
- 平均的な労働者の3倍の年収を得ている(導入時は1,075万円)
- 厚生労働省が示す対象業務(※1)を行っている
(※1)今回、労働政策審議会で5つの対象業務を提示しました。(詳細は下で解説します)
また、導入するにあたり、次の義務が生じます。
- 年間104日の休日を取得させる
- 労働時間を把握する
さらに、次の4つからいずれかの措置を行う義務もあります。
- インターバル措置
- 1か月または3か月の在社時間等の上限措置
- 2週間連続の休日確保措置
- 臨時の健康診断
制度開始1年目で414人が届けられた
厚生労働省によると、実施初年度で高度プロフェッショナル制度の届出が行われたのが、12件で414人だったそうです。
2020年3月末:414人
- 金融商品の開発(2人)
- 金融商品のディーリング(15人)
- アナリスト(27人)
- コンサルト(369人)
- 研究開発(1人)
出典:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(令和元年度)」
高プロの5つの対象業務は?
厚生労働省の労働政策審議会 (労働条件分科会)で提示された対象業務は、次の5つの業務です。
- 金融商品の開発
- 金融商品のディーリング
- アナリスト
- コンサルト
- 研究開発
金融商品の開発
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務を行う者。
「金融商品」は、金融派生商品と同様の手法を用いた預貯金等を含む。
【対象者】
- 金融取引のリスクを減らしてより効率的に利益を得るため、金融工学などを用いた新たな金融商品の開発の業務
【対象外】
- 金融サービスの企画立案又は構築の業務
- 金融商品の売買の業務、資産運用の業務
- 市場動向分析の業務
- データの入力・整理を行う業務
金融商品のディーリング
【対象者】
投資判断に基づく資産運用
有価証券の売買その他の取引
証券会社等におけるディーラーの業務
【対象外】
投資判断を伴わない顧客から注文の取次ぎ
ファンドマネージャーやトレーダー、ディーラーの補助
金融機関の窓口業務
アナリスト
相場等の動向や有価証券の分析・評価、投資に関する助言の業務を行う者。
【対象者】
- 高度な専門知識による分析をして、運用担当者に投資の助言を行う業務
【対象外】
- ポートフォリオを構築又は管理する業務
- 一定の時間を設定して行う相談業務
- データ入力・整理を行う業務
コンサルト
顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務を行う者。
【対象者】
企業に対して経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をする業務
【対象外】
- 調査・分析のみを行う業務
- 助言のみを行う業務
- 個人顧客への助言業務
研究開発
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務
【対象者】
- 新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う開発業務
【対象外】
- 使用者からスケジュールを指示されて行う開発業務
- 技術的改善を伴わない開発業務
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回、労働政策審議会で、5つの対象業務と対象外の基準が提示されましたが、高度プロフェッショナルに相応しい高度の業務が並んでいました。
今後、対象業務の拡大がどのように行われるかを注視していきたいと思います。
なお、働き方改革について、併せて関連記事もご覧ください。
【関連記事】